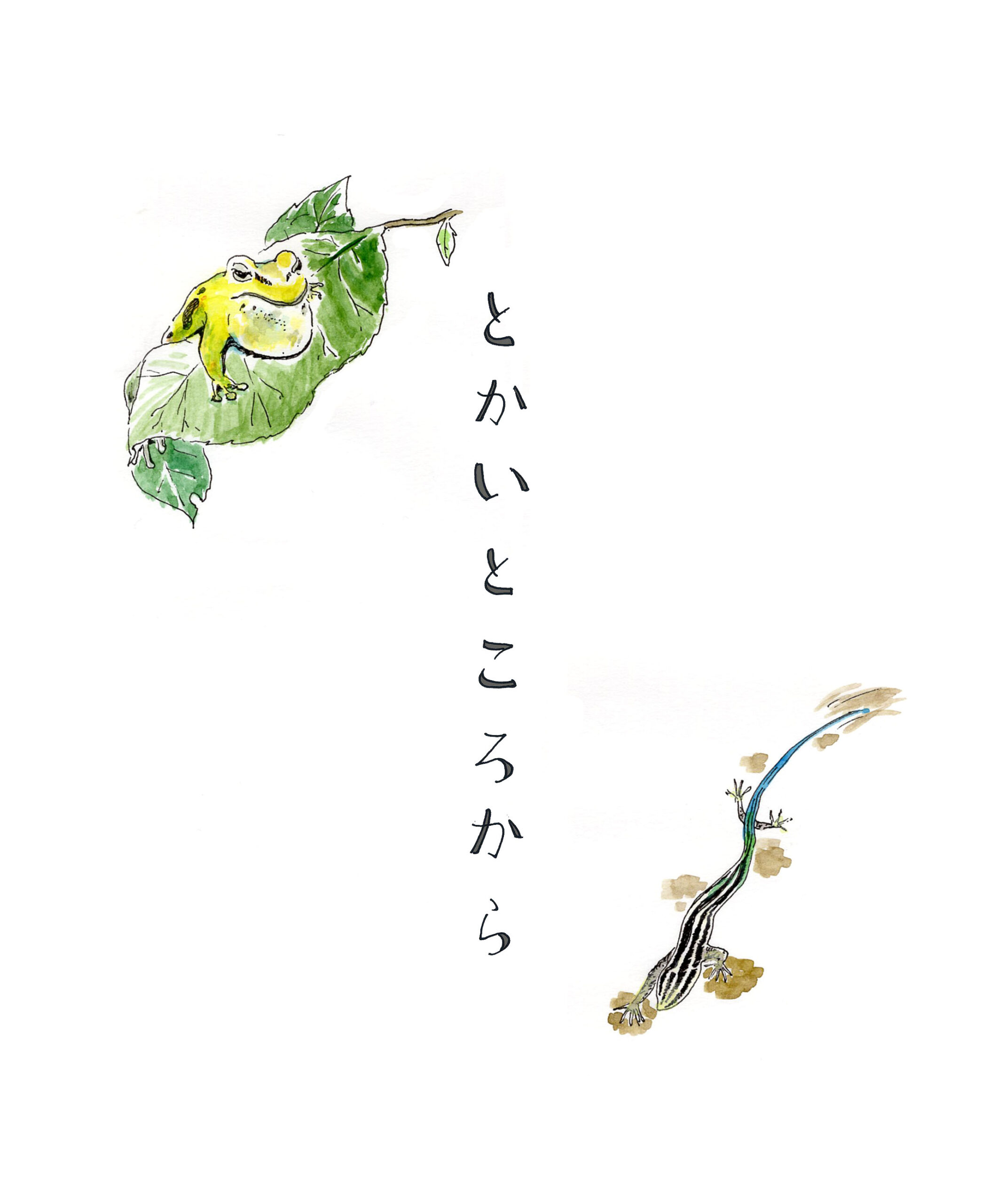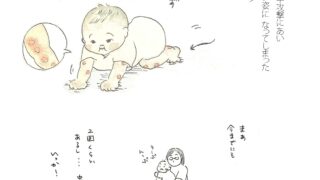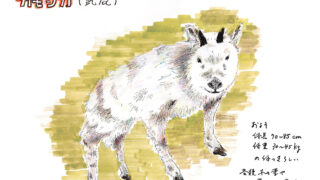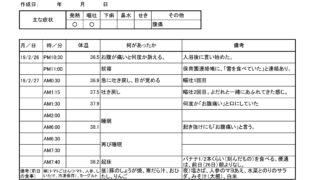*本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。
*画像はすべてクリックで拡大します。
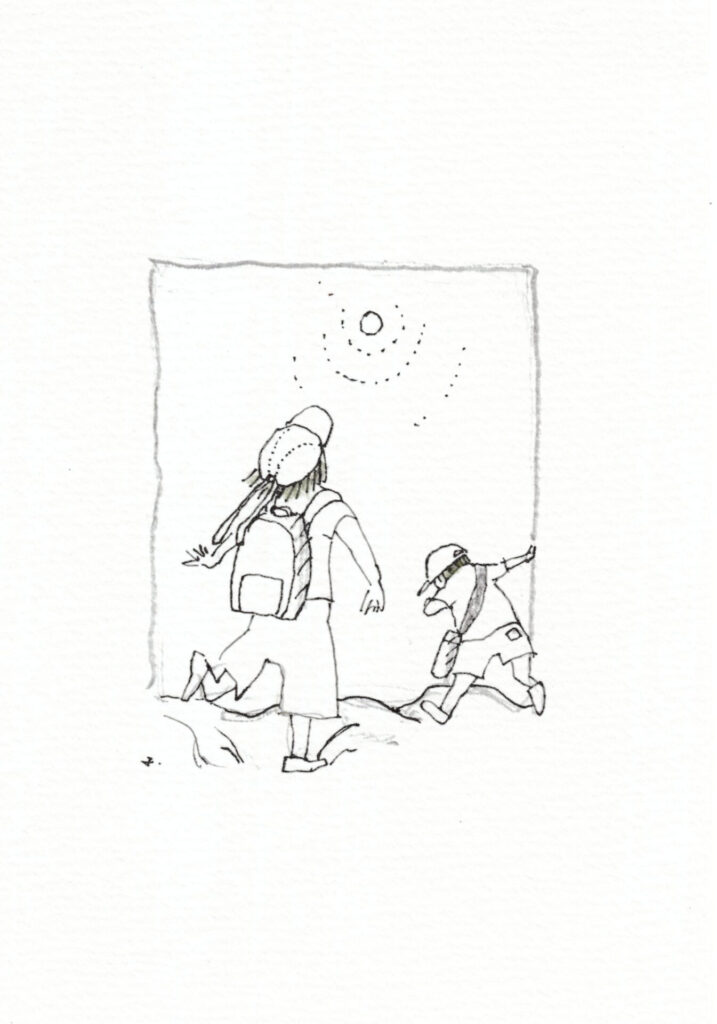
丘を越え 行こうよ
口笛 吹き吹き ・・・
わざわざ丘を越えていかなくとも、
我が家は毎日、丘の向こう。
とかいところの楽しみは、やっぱりこんなこと。
ある日の朝ごはん

*
24年10月某日、午前10時過ぎ。
ねぼすけのいちひめが、やっと起きてきました。
小学生は毎日毎日彼らなりに忙しく、週末には疲れもたまっている様子。
勉強もさることながら、3分間続けての走り込みや600メートルを立派に走ったりなどしている。小学生だった在りし日の自分と比べて、今の小学生の方が随分勤勉に色々なことに取り組んでいるように思われます。
そもそも彼らの小学校は、全校生徒みんなで30人くらいの規模。否応なく、年齢も能力も違う子どもたちが一緒に何かをするということが発生します。
そんな時、いちひめを含めこの辺りの小学生たちは、「身の丈以上」「身の丈以外」のことでも、臨機応変に合わせて、日々を過ごしているように見える。
そのおかげでか。
どの子も揃ってだいたい優しくて、面倒見がいい。
皆それぞれ色々と言いたいことはある環境かと思いますが、「異なる他人に自分を合わせてみる」というこの経験は、大きくなった時にこそ強く活きてくるのではないかと思うよ。
みんな本当に偉い、応援してる。
ということで生活リズムの崩れ云々という意見もあるでしょうが、毎日頑張ってお疲れさんだし、たまのお休みだし。まあ好きに寝かせてあげても良いかなと個人的には思って、好きなだけ寝かせていました。
で、結果的に案の定、朝食が中途半端な時間になってしまった。
と、そこで弟が横目で姉の朝食の用意を見て、
(いいなー。僕も何か、食べたいなあ。)
とでも思ったのでしょう。
「ぼく、おやつ食べる!」
と言い出した。
またこの人は。
定期的に大好きになる、棒のついてる飴ちゃんが食べたいのだと言っています。
「これはね、大冒険の時、食べるんだ!」
ほほう。
そいつはいいね。
「おねーちゃん。朝ごはん、パンでいい?」
「うん。でもマヨネーズとふりかけぬって」
「はいはい。
でね、にたろうが外で飴食べるって言ってるけど、朝ごはん、外で食べる?」
「えー。
・・・
うーん、うん。いいよ。
うん、そうする」
いちひめ、最初は気のない返事でこたつに潜りかけていましたが、ちょっと考えてみて気が変わったのでしょう。
ぱぱっと素早く服を着替えて、準備していました。
…ワンピースを後ろ前逆に着てるように見えるんだけど、言っても本人はそんなことないよと受け流すので、まあじゃあ、多分そんなことは無い、無かったんじゃないかということにしておこう。
*
外に出ると、この日はからっといい天気。
前の日が雨だったので、何だか久々に思える、いい陽気です。
でも気温がぐっと下がりました。お日さまはさしているけど、それよりも風が寒い。
これだけ寒くなると、ヘクサが減るのは有り難いけど。
にたろう、どこ行く?
おねーちゃん、あっち、行こう。 …
さわさわと浮きたつような声を残して、子どもは軽やかに走り去っていきました。子どもは風の子と言いますが、寒くないんだなあ。駆けゆく彼らの後ろ姿は生命力と明るさに満ちていて、どこの誰がどう見ても純粋に「喜ばしいもの」だなと思える。
めいめい、美味しいものを手にもって。
玄関先の階段で並んで腰かけて食べているかと思ったら、またしばらくすると立ち歩いては、飛んだり跳ねたり、あっち行ったりこっち行ったり。
私は日向で、それをぼんやり見ています。もういちいち追いかけなくても、目で追うだけで良い年頃になった。楽になったもんだなと思います。

お隣の敷地には元々家がありましたが、今、更地が広がっています。
長いこと誰も住んでいらっしゃらなかったのですが、その年、持ち主の方が取り壊しを決行されたのでした。今はその分の空き地がぽっかり空いて、その向こうに小さい神社とお地蔵様が見通せる。
食事が済んだ子どもらは、皿やごみくずを玄関にポイ捨てしてったな、と思ったら、また飛び出して行って、今度はその空き地周りでヒーローだか乗り物だか魔導士だかになりきっている。
草花や木の棒を何かのひみつアイテムにしたり、坂道や段差をステージにしたり、それぞれの夢の世界を作っている。
手足も口も始終動いていて、走ったり歌ったり叫んだり、せわしないことこの上ない。一日付き合っていると、どこからそのエネルギーはわいてくるんだろう、と思うほどです。
でも子どもって、そんなもんですね。
私だってそんなにアクティブな子どもではなかったけれど、それでも幼少時「大人はどうしてあんなにすぐ、疲れた、眠いって言うんだろう」と本当に不思議に思っていたものな。
それくらい、子どもは大体、動ける限りはずっと動いていてずっと遊んでいたい生き物なのだと、子どもを育ててようやく知りました。
でもいいよ。
ここでは人は周りに居ないし、誰かの迷惑になることもない。
いちいち、ダメって言わなくていい場所。
玄関開けたら、すぐピクニックに行ける場所。
気力も体力も無い週末の大人には、何て有難いんだろうと思います。
大人になって思うこと
改めて大事だと思ったこと
この町に移住してきてから9年目の終わりにさしかかっています。
このブログを始めた頃に比べると、町のことも、その中に暮らしている人のことも多少は知見を増やすことができました。
自分が気になったり大事だと思ったりしたことは多岐にわたり、記事にしようと書きかけてはまとめきれずに放置されているページも、実は多数あります。
そんな数ある中で、今回はこの日記みたいなぼんやりとしたテーマを選びました。
その理由は、
色々あるけど、ざっくり考えて自分が大事だなと思うことってなんだっけ。
あ、これだっけ。
と言う気持ちになってきたからでした。
いえ、色々と細かいことも、頭にはあるのです。
子どもが大きくなるにつれて、目に入るものがまた変化してきた、とかいとこ暮らし。
不便さの内容も変わってきた。
必要だと思うものも変わってきた。
本当はもっとそんなところを掘り下げて、きれいに整理整頓された内容としてまとめていきたい気持ちもあるのです。
町のことを良く知らない人に「とかいところ」の具体的なあれやこれやを紹介できたらな、と言う気持ちもあるのです。
本音を言ったらこんなふわふわした内容だけでなく、もっとちゃんと「おお、これは!」と思ってもらえるような実践的な情報を紹介したいのです。
でも色々考えていたら、やっぱりよく分からなくなってくる。
まだまだ未熟な、駆け出しの母であり、移住者であり…
何が不便なのか!
何があって、何が無いのか!
何が要るのか!(重要。第一に住民として)
はっきり答えを出してみたいけど、突き詰めてくると、分からなくなってくる。
ある時は白であることが、時としてグレーになったり黒になったりもする。
良しと悪しが、表裏一体の現象として現れていることも多い。
そして当然ながら、人によって答えは変わる。
何が良いのか、悪いのか。何をどうするとより良くなるのか。
良いって何か、悪いって何か。
誰にとってか。
わからん。
私はこんな風にここ数年、「とかいとこ暮らし」の概要が自分でもあまり上手くつかめなくなるという、「とかいとこ迷子」(仮称)になっていました。
そんなうろうろした2~3年の挙句、最近は何となくま、いっか、という気持ちになってきた。
そして原点回帰的な気持ちで、改めて見直せることもできてきた。
なぜ、ここでないといけないのか。
ここの何が、嬉しいのか。
いとしいのか。
場所を変えてもあるような「ふつうの喜び」だと思っていたけれど、「場所を変えても存在するだろうけど、やっぱりここだからこその喜びの形になっているようだな」。
そんな気持ちになってきた。
そんな気持ちでまとめたのが、今回の話です。
「不便だ」と思うことはシチュエーションによって変わっていくけれど、「ここに住んでいたい」と思うおおもとの気持ちがあまり変わっていなかった。
自分にとっては、ささやか、でも目の覚めるような発見でした。
そして嬉しかった。
不満の中身は変わっていっても、満足のタネは、割と不動のものとしてそこにあってくれたということが。
言い換えてみれば、それはここで暮らす上で、案外「一番大事な要素」ということかもしれません。
私や旦那さんが、将来的な不安要素を色々と想定しながらも「やっぱりここに住んでいたい」と思う理由は、現時点では以下のような内容としてまとめられます。
ここなりの「自由」がある
こんなことを言うと実家の父母はまた悲しがるかと思うのですが、実はたまに帰省して非日常を楽しんだ後、山の中の家に帰ってくると、何だか訳もなくほっと安堵する感覚に陥ります。
あー、帰ってきたぞー。
おーい、帰ってきたぞー。
ただいまー、ここが家だぞー。
空が広いぞー、山が見えるぞー。
心からくつろいだ気分になって、そして大声をあげて、のびのび体を伸ばしたくなります(実際にそうしたりもします)。
何も実家が嫌なわけでは、もちろんない。
ただ比べてみると、今となってはどうしてもこちらの環境の方が、私にはより「合っている」のだと思えてきます。
なんでだろう。
色々あると思うのですが、その理由の一つとして挙げられるのが、「人の目を気にする必要があまり無いこと」があると思います。
これは子どもと一緒にいる場面では、私にとっては特に大きな理由となります。
人の多いところに行くと、誰かの「迷惑」になってしまう行動は、おのずと増えます。
子どもが本能的にやりたがることの多い、「走り回る」や「大声を上げる」も、場所によってはアウトです。
とは言え彼らは幼ければ幼いほど、他人の理屈を受け入れることは何と言っても難しい。
走りたい!
叫びたい!
遊びたい!
…等々の衝動を抑え込むのは、たいてい大人の役割になります。
が、これがなかなかに骨が折れる仕事です。
私はそういう場面では、
・ひとまず子どもに、「人の迷惑になるからやめよう」と説く。
・その裏で「我が子の行動が人に迷惑だと思われているのではないか。早いとこカームダウンさせないと」と考える。
・「迷惑だと思われているとして、どの程度思われているだろうか」とかも、考える。
・更に「逆に度々“人の迷惑になるからだめだよ”と言っている私こそが、実際には耳障りに思われているんじゃないだろうか」と言う可能性を考え出す。
・このように複数の矛盾する可能性を想定し、それを予防するようにアンテナを張って行動する。
こんなことをやっているもので、最終的にめちゃくちゃ疲労感を覚えてしまいます。
何も私だけの特徴ではないでしょうが、支援センターなどでの子どもの遊ばせ方を見ていると、自分は比較的細かい事柄まで気にしてしまって、結果的に子どもにも行動を遠慮させる、ということをしてきたんだろうな…と今更ながらに反省するところが多々あります(特に長女の頃)。
逆にちょっとくらいの迷惑はお互い様と、大らかに、良い塩梅で子どもを好きにさせられる保護者さんのやり方、憧れる。
前々から方々で書いていますが、この町では顔見知りが多く、子どもに対して寛容で面倒見の良い大人が多いと感じます。
そんな環境だと、周りに人がいてたってやっぱり気心は知れているし、安心材料も多い。多少のことは「子どものすることだからいいよ」「それくらいがいいよ」と言ってもらったり、「そんなことしたら駄目だよ」と直接子どもに注意してくれたりする。
そして何より、子どもを取り巻く大人の大多数が、「どこかのガキ」ではなく「〇〇さんのとこの子」「町の子」として、温かく愛情深い目で子どもを見ているのが分かる。
だから安心して、のびのび過ごせられる。子どもを、そして自分自身をも。
都会の街中で私が気疲れしてしまうのは、こういうところなんだろうなと思います。顔見知りでもない、そもそも人口が多い、そんな不特定多数の人の多いところでは、色々な人が居るし、色々な考えも感覚もある。その融通の加減が、当たり前だけど分からない。
そういう場ではルールやマナーや常識といった「一般的な決めごと」が効果を発揮するのだろうな、と思う一方、そんな「決めごと」の内容も実際には個人間でかなり振れ幅があるように思うので、やっぱり分からない。
だからそういう場所から我が家に帰ると、正直ほっとする。
何をしてもらってもいいし、一緒に大声も出せる。変なポーズも絶叫も、男児が好きそうな「言っちゃいけない言葉」だって、どんどん言ってみていい。
周りに人が居ないから、誰の迷惑にもなりません。
隠れなくても、隠さなくても良い。
ここでは、自由だ。
都市部なりの「自由」があれば、とかいところならではの「自由」も存在する。
ささやかなことではあるけれど、子育てをしていると、割とそんなことが自分にとっては大きかったりする。
そういうことを、9年目の今、やっと認識しています。
「広場」の世界は、なんにでもなれる

ここは、
剣と魔法の世界。わたし魔法使い。
乗り物が命を持っている世界。ぼくはそれと融合して、自由自在に変形できる。
ここは、
遠くてなかなか行けないじいじばあばの家のある街。
夜にまばゆい、ネオンの灯る長い階段。
幼い頃行って素敵だった、海水浴場の高級旅館。
◯◯したつもり、行ったつもり。
子どもたちは、どんどん自分が一体化したい「好き」たちを外に拡張していきます。
言うなれば「ごっこ」。
実際どこでだってできる遊びですが、私の幼い頃は、大体屋外のだだっ広いところでやっていました。公園だったり、住んでいた地域の集会所の前だったり、学校の運動場だったり。
「広場」的な場所と相性がいいのかな。
ドラえもんだったら、土管のある<いつもの空き地>のような場所。
かえりみて思うのは、我が家の周りは「広場」的な場所ばっかりじゃん、ということです。
なので基本、うちの周りは自由世界。
何にでもなれるし、どこへでも行ける。
我が子たちもご多分に漏れず、散歩に出かけると大体、何かになってピンチに陥ったり戦いを始めたりします。
なんにでもなれるのは、実は大人にとっても同じことで。
運動不足の体をせめてもテコ入れする為に、毎朝ラジオ体操の会場にもできるし(まあすぐにさぼるのですが)、
気分が良かったら、歌詞の良く分からん歌を適当に歌ってカラオケ気分(実は周りの畑地にどなたかいらっしゃったりするのかもしれませんが)。
ウォーキングコースとして山道を上がったり下ったりすると、季節の移り変わりが良く分かります。
桜が咲いていたら花見。
空がきれいだったら星見と月見。
秋に山の葉が色づいたら行楽です。
現実には家を出たらすぐに到着できるような超近場でも、わざわざリュックサックにおやつやごはんや詰め込んで、旅行気分に登山気分。
アレルギー持ちのお友達がお母さん手作りのお弁当持参で遊びに来てくれたら、玄関先にちゃぶ台出して、おやつもリュックに詰め込んで、外で昼食・遠足気分を演出します。
そういうのが、私は大好きです。
そういうのの為なら、多少面倒くさくても、何かやっちゃう。
サイコー。
ここ数年、ぐんと多忙を極める旦那さんと久々に散歩をしてリフレッシュしたある日、彼は「やっぱこれなんだよな~」的なことを言っていました。
この家の、この場所の、いいところ。
ここで過ごす上で私たちにとって大事なのは、多分これなんだろうねと。
緑あふれる山と空が、ありふれた日常になってしまったとしても。
家を出たらば、ピクニックができる。
今、ここ、
を楽しめること。
そうだね。
私もそれを大事だと思い、これからもそう思っていけたらなあと願っています。
そのためには特になんでもない日に手弁当を作り、あり物のおやつと水筒を持たせて探検に出かけるつもりになり。
大体急遽思い立ち、即日決行。
子どもたちは子どもたちで、お気に入りのおもちゃを持ってきたり、その辺の棒やら持ってきては何かに見立てて、「つもり」に乗っかってくれます。
今のところ。
*
さて、25年のGWには、キャンプ気分でテントを張ってみました。
実はこれは父母から譲り受けたテントで、私がちょうどいちひめくらいの年頃の時、はじめて山でキャンプをした時の思い出深い品でもあります。
その後あまり使われないまま時間が経ってしまったので、ぱっと見はまだまだきれい。素材は劣化していると思うので耐久性については怪しいですが…。
テントを組み立てる私を横目に、子どもたちはめいめいリュックサックになんだかんだ詰め込み、黙々と家から運び出しています。多分、ほぼ9割がたキャンプに要らないものっぽいな。
私ができたーと宣言する前から、彼らはいそいそと中に陣取り始めました。
巣の中でじゃれる生き物のように騒ぐ子らを押しやって、自分も中に入って寝転んでみると、
あ、なんか気持ちいい。
見上げる天蓋は緑。
入口から見える景色も、一面の早緑。
ぜんぶ、緑の世界。

子どもたちはその後も引っ越しよろしく、意気揚々と枕やらタオルケットやら持ち込み、その日はそのまま昼もそこで食べていました。
五月の陽気を受けると日中は少し暑いくらいでしたが、夕方になると風が吹いて気持ちの良い場所になりました。
楽しかったね、またやろうね。
そんな思い出が一つ、また一つと、私たちと彼らの間にちまちまと積み重ねられていく。
一緒にいるようで実は別の人生を歩む親と子の間柄としては、そんなことが実は長い目で見ると存外に得難く、貴重なことなのかもしれません。
おまけの動画を添えて。
(2025年8月、暑い夏です)